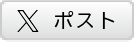2000年5月、「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名・認証業 法) が成立し、翌 2001年4月から施行されました。 わが国においては、紙の文書にする署名や押印に関する一般的な法的要 件を定めた法令は存在しないため、諸外国の電子署名法のように、電子 署名に手書きの署名と同等の法的効果を与えるための法律が存在しなく ても、電子署名が付された電磁的記録を手書き署名や押印のある文書と 同等に扱うことに問題はありませんでした。わが国の法令において、手 書きの署名または押印のある文書に法的効果を与える唯一の規定であっ た、民事訴訟法の「文書の真正な成立の推定効」 (A さんの署名がされ ている文書は、それを覆す別の証拠がでてくるまでは、訴訟において、 A さんが自分の意思で作成した文書として取り扱われるという効果) に ついても、何が署名であり、何が押印であるかについての規定は存在し ないことから、電磁的記録についても、裁判官が署名の付された準文書 であるとの心証を形成することができれば足り、電磁的記録に契約書等 の文書と同等の効力を与えるために立法が不可欠であるという状況では ありませんでした。 しかしながら、当時の国際的な動向として、特に、手書きの署名等の要 件や効果が法定されている国々を中心に、電子署名に手書きの署名と同 等の法的効果を与えるための電子署名法の立法が相次いで行われていた ため、わが国において電子署名法の立法を行わない場合は、日本では電 子署名が手書き署名と同等に扱われないのではないかという誤解を生み、 国境を超えて行われる電子商取引の分野等においてわが国企業等の競争 的地位によくない影響が生じることが懸念されました。また、電子署名 を署名と同等に扱うことに法令上の障害が存在しないとしても、訴訟に おいて裁判官がどのような判断をするかの予見ができにくい状況では、 企業等が電磁的記録による契約等に二の足を踏んでしまうことも心配さ れました。 そこで、わが国の法令において、手書きの署名または押印に法的効果を 与える唯一の規定であった、民事訴訟法の「文書の真正な成立」の推定 効を、電子署名がされた電磁的記録にも与えることを内容とすることで 電子署名法の立法が行われたものです。 また、どのような電子署名がこのような推定効を与えられ得るかに関す る利用者の予見可能性の向上や、信頼できる電子証明書の発行業務(認 証業務)の基準を明らかにすることによる電子署名の利用促進を目的と して、「その方式に従って本人にしかできない電子署名」の要件や、認 証業務の認定制度が併せて規定されています。このため、わが国の電子 署名法は、「電子署名・認証業法」という略称でも分かるとおり、電子 署名の効果、要件のほかに、電子認証業務に関する規定が多く盛り込ま れたものとなっています。
参考文書(日本語)
-
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html
-
電子署名及び認証業務に関する法律の概要
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denshi_syomei/2-1.pdf
-
電子署名・電子認証ホームページ
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/ninshou-law/law-index.html
Weekly Report 2008-04-09号 に掲載